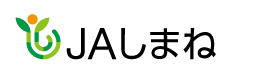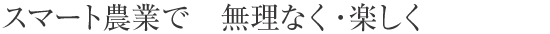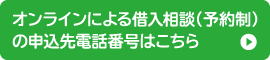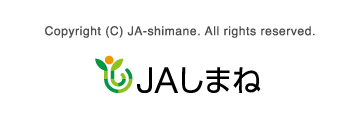つながるコラム「絆」 vol.91 吉賀町 ・ 井川津多夫さん
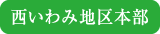

農事組合法人 ごんごんじいの郷 代表理事 井川津多夫さん (66歳)
西いわみ地区本部
「ごんごんじいの郷」の誕生

吉賀町真田地区。清流日本一にも選ばれた一級河川・高津川が流れ、山々に囲まれた自然豊かな地域です。ここではかつて、多くの農家が自分の田畑を耕してきましたが、近年では高齢化により、耕作放棄地の増加や農地管理が大きな課題となっていました。そんな中、平成24年度から農林水産省が開始した事業の「人・農地プラン」を策定するにあたり、真田地区でもアンケート調査や関係機関との協議を実施。その結果、地域で圃場整備事業に取り組むことを決意しました。圃場整備事業を行うには、法人の設立と高収益作物の導入が条件となっていたことから、地域の農地を共同で管理・活用していく体制として農事組合法人を令和3年2月に設立。その名も、「ごんごんじいの郷」。地元で親しまれてきた子どもの見守り神様「ごんごんじい」にあやかり、地域の未来を見守る存在になりたいという願いが込められています。「この地域では"自分たちで自分たちの農地を守っていきたい"という意識が根付いていた。自分たちで次の世代に引き継げる形を残したかったんです」と、代表の井川津多夫さんは当時を振り返ります。地域の現実と向き合い、未来の農業を模索する挑戦が、ここから始まりました。
地域にあった柔軟な農地管理

「ごんごんじいの郷」の運営は、農地の貸し手と作業の担い手が共に参加しています。これは、福井県などで取り入れられている「まるっと中間管理方式」を応用し、地域の実情に合わせた柔軟な農地運用の仕組みです。「自分の土地は自分で耕したい」という組合員もいたため、法人が一度農地を預かり、耕作を希望する方には作業をお願いし、それ以外の農地は法人で管理するという、誰もが納得できる農地管理の仕組みを構築しました。この方法により、農地の管理がスムーズに行えるだけでなく、農業の継続が難しくなった場合にも法人で対応できる体制が整い、地域の農業を中長期的に支える役割となっています。
スマート農業で、無理なく・楽しく

現在、「ごんごんじいの郷」では、真田地区の約17ヘクタールの農地を管理しています。圃場整備により農地が大規模化され、自動田植え機や、自動給排水装置、どこからでも機械が出入りできる「ターン農道」など、スマート農業を実践できる環境を積極的に整えてきました。自動で操作できる田植え機や、水の状況をスマホで管理できるアプリ「ワタラス」も活用。さらに畦畔を2mに広げることで、草刈りもトラクターで行え、炎天下でも冷房の中で快適に作業が進められます。農業というと「きつい」「大変」といったイメージがありますが、省力化や軽労化を進めることで、高齢化や天候などの課題にも対応し、"続けられる農業"を実現できています。
仲間の支えと雰囲気の良いつながり

「ごんごんじいの郷」の大きな特徴は、みんなで支え合う体制が整っていることです。「この法人の良いところは、一人に負担がかからないこと。部門ごとにリーダーがいて、みんな協力的だから続けられるんです」と井川代表は話します。水稲・野菜・機械管理・総務の4部体制で役割分担がされており、それぞれのリーダーが調整を担ってくれるおかげで、負担が偏らないようになっています。作業は基本的に一人のオペレーターがトラクターで行い、田植えやキャベツの収穫など必要な時だけ数人が集まります。稲刈りなど負担の大きい作業は外部に委託しており、年間の稼働日数はごくわずか。作業の連絡や出欠確認は、LINEで手軽にやり取りし「○日に田植え手伝える人?」といった気軽なやり取りが飛び交い、必要なときに自然と人が集まる体制です。作業中も和気あいあいとした雰囲気で、皆で冗談を言い合いながら、笑顔で楽しそうに農業に取り組んでいます。また、田植えなどの作業後には懇親会として、集まった仲間同士で労をねぎらう場を設けています。「やっぱり一番大事なのは、飲み会」と笑う井川代表。「農業は"楽しく・楽に"やらないと続かない。だからこそ、新しい技術や分担の仕組みが必要なんです」と語ります。無理なく関われるからこそ、地元の人たちが農業を楽しみながら続けられる。そんな温かなつながりが、「ごんごんじいの郷」の農業を支えています。
この地域で農業を続けていく仕組みづくり

現在の作付けは、水稲を中心に飼料用稲(WCS)やキャベツ、タマネギなど。高収益作物の導入や乾燥・調整作業の外注、スマート農業の活用により、限られた人手でも最大限の成果を出せる工夫がなされています。それでも「この地域の農業者の平均年齢は70歳を超え、自分も含めて高齢化が進んでいる」と話す井川代表。今後は50代の世代にバトンを渡していくとしながらも、さらにその先の後継はまだ見えておらず、大きな課題となっています。この地域の取り組みに共感してくれる若者がいれば、ぜひ迎え入れたいとも語ります。大切なのは、"この地域で農業を続けていける"仕組みを作り続けていくこと。そんな想いを大切にしながら、これからも新しいやり方での挑戦を続けていきます。