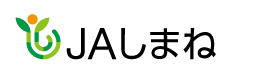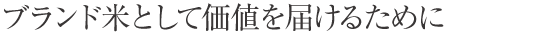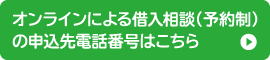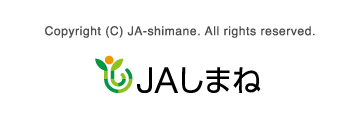つながるコラム「絆」 vol.84 隠岐の島町 ・ 村上淳一さん
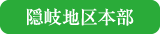

村上 淳一さん(43歳)
隠岐地区本部
隠岐古来の農法にヒントを得たブランド米

隠岐諸島は暖流と寒流がぶつかる海域にあり、気候も生態系も独特。海上で発生した霧が大地に降り注ぐため、土壌のミネラル分が豊富なのも特徴です。そんな環境で作られているのが「島の香り 隠岐藻塩米」。耕作地が限られる離島の隠岐の島町で、付加価値が高く〝ブランド米〟の価格で流通できる米を作り島外へ送り出そうと、約20年前から生産が始まりました。 栽培方法のルーツは、海岸に打ち上げられたアラメなどの海藻を肥料にしてきた隠岐の伝統的な農法。これを現代版にアレンジし、島内で作った藻塩の水溶液を散布。土だけでなく葉からもミネラルを吸収させています。炊き上がった米は粒が立っていて弾力が強く、冷めてもプリッとしているため食べ応えがあります。
藻塩米栽培とともに地域の米作りを担う

留島の香り隠岐藻塩米生産者協議会の会長を務める村上淳一さんは生まれも育ちも隠岐の島町。代々続く農家を継いで20年ほど経ちましたが、実は大学時代までは教師を目指していたそうです。村上さんは「農家になる気はなかったのですが、大学3回生の年に父が急死したことをきっかけに『後を継いで頑張ってみよう』という気持ちに。卒業後に帰郷しましたが、農業の知識はゼロ。本当に大変で地域の農家さんやJAの職員さん、県の普及指導員さんに助けていただき、今があります」と当時を振り返ります。

時代の変化を読みながら新たな挑戦も

「島の香り 隠岐藻塩米」の最大の特徴でもある藻塩水溶液の散布。水溶液を散布すると稲はしっかりとし、茎や実はもちろん、葉もカヤのように固く鋭くなるのだそう。適度な量の塩水を散布することで程よくストレスがかかり、稲が栄養を蓄えようとするためおいしくなると言います。

ブランド米として価値を届けるために

「島の香り 隠岐藻塩米」は厳選した米を取り扱う専門店のみで販売されています。その理由は価値を保つため。島根の米の生産量は全国の1%程度。さらにその1%が隠岐で生産された米で、藻塩米はさらにその10%ほどしかないとても希少なお米です。村上さんは「だからこそ安売り競争に巻き込まれないよう、価格が高くても『おいしいから食べたい』と求めてくださる人に届けていく。そのためには環境や生産方法、おいしさの理由をきちんと説明して売ってくれるお店に並べる必要があります」と熱く語りました。
年に数回首都圏へ出かけ、ブランド米を取り扱う有名店で意見を聞いたり、試食販売でお客さんの声を集めたりとリサーチも欠かしません。努力の甲斐あってリピーターも増えていますが、その一方で「米づくりが魅力ある産業でなければ持続は難しいでしょう。価格も適正なものになってほしいですね」と課題も口にします。
忙しい日々の癒やしはお酒。地域の仲間たちとの飲み会が頻繁にあり、心安らぐひとときになっているそうです。楽しい会話からアイデアが生まれたり、新しいつながりができたりすることも。仲間と過ごす時間が挑戦する力になっているようです。
隠岐の独自の環境と伝統的な農法を融合させた「島の香り 隠岐藻塩米」。地元の魅力がつまった藻塩米がさらに全国に広がるよう、村上さんの挑戦はこれからも続きます。